0から分かる!
就労移行支援とは
就労移行支援がどのようなサービスなのか、利用するメリットや選び方をわかりやすくご説明します。
就労移行支援とは
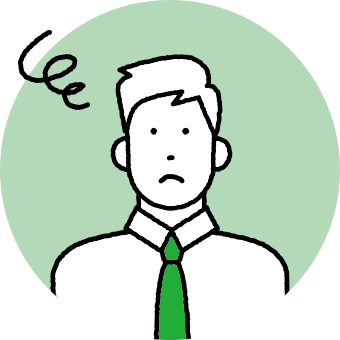
就職を考える上でこのようなお悩みはありませんか?
- 就職しても働き続けられるか不安
- 障害とどう付き合いながら働いたら良いかわからない
- 自分に合う仕事がわからない
- 就職活動がうまくいかない
このようなお悩みを持っている方に知っていただきたいサービスが就労移行支援です。
就労移行支援の役割

就労移行支援とは、障害のある方が働くために必要なスキルを身につけるトレーニングや、就職活動のサポートを受けられる「通所型」の障害福祉サービスです。
就労に対する不安は、健康管理や人間関係、職業スキル、就職活動など人によってさまざまです。
その不安を課題に変え、解決できる場所が就労移行支援事業所です。
就労移行支援を利用するメリット
就労移行支援事業所を利用するメリットは次の5つがあります。
就労移行支援事業所を利用するメリット
-
1
企業が最も重要視する健康管理の力を身につけられる

-
2
長く安定して働く上で必要な自身の障害とうまく付き合う力を身につけられる

-
3
障害者就労に詳しいスタッフに希望する就労に向けた専用のプランを立ててもらえる

-
4
通いながらスキルアップ研修やトレーニングを受けられる

-
5
就職サポートはもちろん、就職後も職場定着のサポートを受けられる
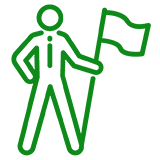
どんなサービスが受けられるの?

長く安定して働き続けられるようになるために、就職のための準備から就職後の職場定着まで、一貫したサポートを受けられます。
就職まで
職業訓練
長く安定して働き続けるために必要な知識を研修や職場実習で学ぶ
- ビジネススキル
- コミュニケーションスキル
- 体調管理スキル
など
就職活動サポート
- キャリアカウンセリング
- 応募書類作成
- 面接対策
など
就職後
職場定着サポート
- 入社後の相談対応
- 企業への環境調整依頼
など
サービス利用の流れ
就労移行支援を利用するまでの流れと就職までの流れについてご説明します。
利用開始までの流れ
-
STEP:1
お問い合わせ・見学予約
- STEP:2 見学・説明会参加
- STEP:3 体験通所 ※就労移行支援事業所によって体験通所ができるところ、できないところがあります。
- STEP:4 受給者証の申請・手続き
- 利用開始!
就職までの流れ
- STEP:1 職業訓練を受ける
- STEP:2 サポートを受けながら就職活動をする
- 就職!
- STEP:3 職場定着のサポートを受ける
就労移行支援事業所にはどんな種類があるの?
対象とする「障害」が違う
次の2つの種類があります。
障害種別を問わない総合型事業所
さまざまな障害のある方が一緒になって訓練を受けます。全国的にこのタイプの事業所が多いです。
自宅の近くで通いたい方や、もくもくと訓練を受けたい方には向いています。
特定の障害に特化した特化型事業所
うつ症状専門や発達障害専門など、特定の障害の方だけで、各障害に特化した専門的な訓練を受けることができます。
周りは自身と同じ障害と向き合う方たちなので、障害の理解を深めたい方やそういった仲間と訓練を受けたい方に向いています。
目指せる「就職先」が違う
軽作業・事務系の職種への就職を目指す事業所がメジャーですが、特定の分野に特化した事業所もあります。
例えば、製造系職種への就職を強みとする事業所では、「作業訓練(仕分け、組み立て、清掃など)」や「ピッキング」などの研修を行っています。
その他にも、プログラミングやWebデザインなどの「ITスキル」や、「接客」、「調理補助」など、さまざまな専門スキルが身につけられる事業所があります。
未経験からでもアイティースキルが身につく就労移行支援サービス アットジーピージョブトレアイティーウェブ

専門的なITスキル「Webデザイン」「プログラミング」スキルと、安定就労のための就労スキルがバランスよく身につきます。
就労移行支援と就労継続支援の違い
就労系福祉サービスには、他にも「就労継続支援」というサービスがあります。
名前は似ていますが、「就労継続支援」と「就労移行支援」はまったく違うサービスです。
2つの違いは、「2年以内に一般就労が可能か」という点です。
2年以内に一般就労を目指せる場合は、「就労移行支援」を利用し、就職に必要なスキルを身につけ就職を目指します。
2年以内に一般就職できるイメージが持てない場合は、「就労継続支援」事業所で実際に働くことを通じて自信をつけていきます。
また、「就労継続支援」は、さらに種類が分かれて、就労継続支援A型と就労継続支援B型の2種類のタイプがあります。
詳しくは、以下の図をご覧ください。
| 就労移行支援 | 就労継続支援 | ||
|---|---|---|---|
| 就労継続 支援A型 |
就労継続 支援B型 |
||
| 目的 | 就職に必要な スキルを身につける ためのトレーニング・ サポートを受ける |
一般企業への就職が 困難とされる方が トレーニング・サポートを 受けながら 就労の場として働く |
|
| 対象者 | 一般企業への 就職を希望する方 |
現時点で一般企業への 就職が難しい方 |
|
| 対象年齢 | 65歳未満 | 制限なし | |
| 利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | 定めなし |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 賃金・工賃 | 基本なし ※一部事業所では 場合によりあり |
あり | あり |
生活や体調に不安がある場合は「自立訓練」
他にも、通所型の福祉サービスがあります。
「自立訓練」というサービスで、障害がある方の「生活」に関する相談や助言などを行うサービスです。
利用期間は2年間で、自立した日常生活を送るための訓練を行います。
就職はまだ考えられず「生活や体調に不安がある...」という方は、就労移行支援や就労継続支援の前に、自立訓練からスタートするという手段もあります。
就労移行支援事業所の選び方

全国に約3,300ヶ所もある就労移行支援事業所の中から、自分に合う事業所を見つけることは大変です。
ここでは、就労移行支援事業所の選び方をご紹介します。
まず、あなたは就職して働き続けるにあたってどのような不安がありますか?
その不安を解消するために何を解決する必要がありますか?
就労移行支援事業所は施設によってカリキュラムや支援メニューもさまざまです。ご自身の解決したい課題が解決できるカリキュラムや支援メニューが充実した就労移行支援事業所を見つけたいものです。
あなたがこの記事を見つけたように、インターネットで「就労移行支援事業所」と検索して見つける方法の他に、次の3つがあります。
自分に合った就労移行支援事業所の探し方
-
1 市区町村へ相談
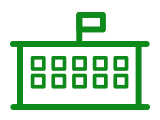
お住まいの市区町村の障害福祉課で就労移行支援事業所について尋ねてみる方法があります。
市区町村によっては、市内の就労移行支援事業所の所在地や特徴を一覧でまとめて冊子化しているところもあります。 -
2 専門機関へ相談
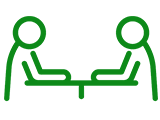
通院先(主治医、ケースワーカー)、障害者就業・生活支援センター、就労支援センター、相談支援事業所、ハローワーク等の職業紹介事業者などに相談してみましょう。
-
3 就労移行支援事業所の検索サイト

レストランや旅館を検索できるサイトが沢山あるように、就労移行支援事業所を検索できるWebサイトも複数あります。
就労移行支援事業所の検索サイトでは、各事業所の特長や所在地、カリキュラム等の情報を得ることができます。
多くの就労移行支援事業所があるため選ぶのは大変ですが、あなたに合った方法であなたに合った就労移行支援事業所を見つけてください。
利用にかかる費用・賃金
利用料金
就労移行支援サービスは、多くの方が無料で利用されています。
利用料金は、前年度の世帯収入状況によって、「無料の場合」と「自己負担が発生する場合」があります。
自己負担の上限金額は、前年度の世帯収入状況に応じて、負担上限月額が月額0円、9,300円、37,200円の3区分が設定されています。
世帯収入とは?
ご本人の収入プラス配偶者の収入
※親の収入は含まれません。
自己負担の上限金額(月額)についての詳細は、次の通りです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム等利用者を除きます。※3 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
ご自身の利用料金がいくらになるかは、市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。
atGPジョブトレの利用者の方の多くは、無料で通所されています。
交通費
原則として交通費は自己負担ですが、市区町村によっては補助が出る可能性があります。
昼食
原則として昼食の提供はありません。
就労移行支援事業所によっては昼食を提供しているところもあります。
賃金
就労移行支援事業所では、基本的に賃金の支払いはありません。
就労移行支援事業所内のプログラムの一環として業務を行うこともありますが、多くのケースでは一般企業で働き続けるために知識と能力を訓練するための「仮想」の業務だからです。
ただし、一部のケースでは外部から実際の業務を委託し、訓練の一環として業務を遂行している事業所もあります。その場合は業務遂行の対価として賃金が支払われます。
利用条件

就労移行支援事業所を利用するには、次の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
-
1 一般企業で働くことを希望する方
※一般企業ではなく、就労継続支援A型やB型等で福祉的な支援を受けながらの就労を目指す場合は、本項目は当てはまりません。
-
2 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがあること
※障害者手帳を持っている方はもちろん、持っていない方も医師の診断や自治体の判断によって利用できます。
-
3 18歳以上で満65歳未満の方
-
4 離職中の方(例外あり)
※休職中の方が、職場復帰を目的としてご利用いただくことも可能です。
就労移行支援事業所受給者証の発行
就労移行支援事業所を利用するためには、お住まいの市区町村の障害福祉課で障害福祉サービス受給者証の申請書の提出が必要です。
これを「就労移行支援事業所受給者証の申請手続き」と言います。
受給者証申請の流れ
- STEP:1 市区町村の障害福祉課で申請書を提出
-
STEP:2
認定調査員による訪問調査
あなたの生活状況や働く意欲を確認するための面談です。
面談の内容で、サービス利用の可否が判定されます。 -
STEP:3
受給者証の発行
無事にサービス利用が認められ、相談支援専門員が作成したサービス利用計画を提出すると、「就労移行支援受給者証」が発行されます。
手続き方法は自治体ごとに異なります。
就労移行支援事業所「atGPジョブトレ」では、受給者証の発行手続きにあたってスタッフがサポートしますので、ご安心ください。
障害者手帳は必要?
障害者手帳を持っていない方も利用することができます。
障害者手帳を持っていない場合は、主治医の意見書が必要となりますので、まずは主治医にご相談されることをおすすめします。
利用できる期間
就労移行支援事業所の利用開始から就職が決まるまで、原則最長2年間と定められています。
利用期間の延長はできる?
2年間を過ぎてしまった場合でも、市区町村と事業所により就職の見込みがあると判断された時は短期間の延長が認められるケースもあります。
就労移行支援事業所は複数回利用できる?
「退職後に、もう一度就労移行でトレーニングして再就職したい」、「通っている就労移行支援事業所が合わないので別のところに行きたい」という方もいらっしゃるかと思います。
就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば別の就労移行支援事業所を利用することが可能です。
ただし、ケースバイケースのため、市区町村の障害福祉課や就労移行支援事業所にご確認いただくことをおすすめします。
あなたはどのタイプ?タイプ別通所シミュレーション
3つのタイプから自分と似ているタイプを選んで、
atGPジョブトレの通所イメージを膨らませましょう!












