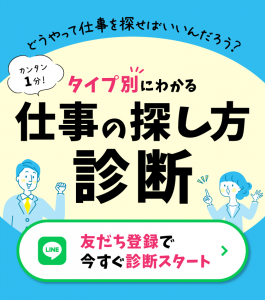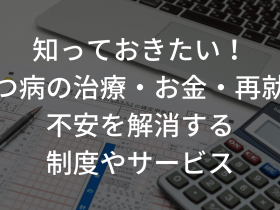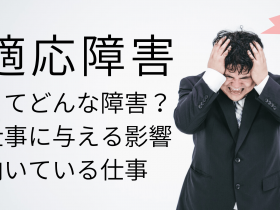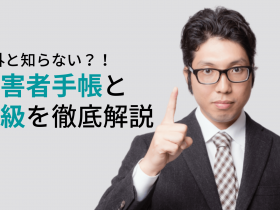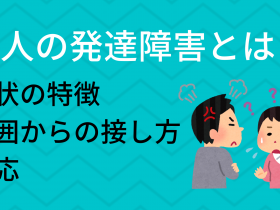記憶障害になると日常生活への変化は?予防・対策法をご紹介
更新日:2024年06月14日
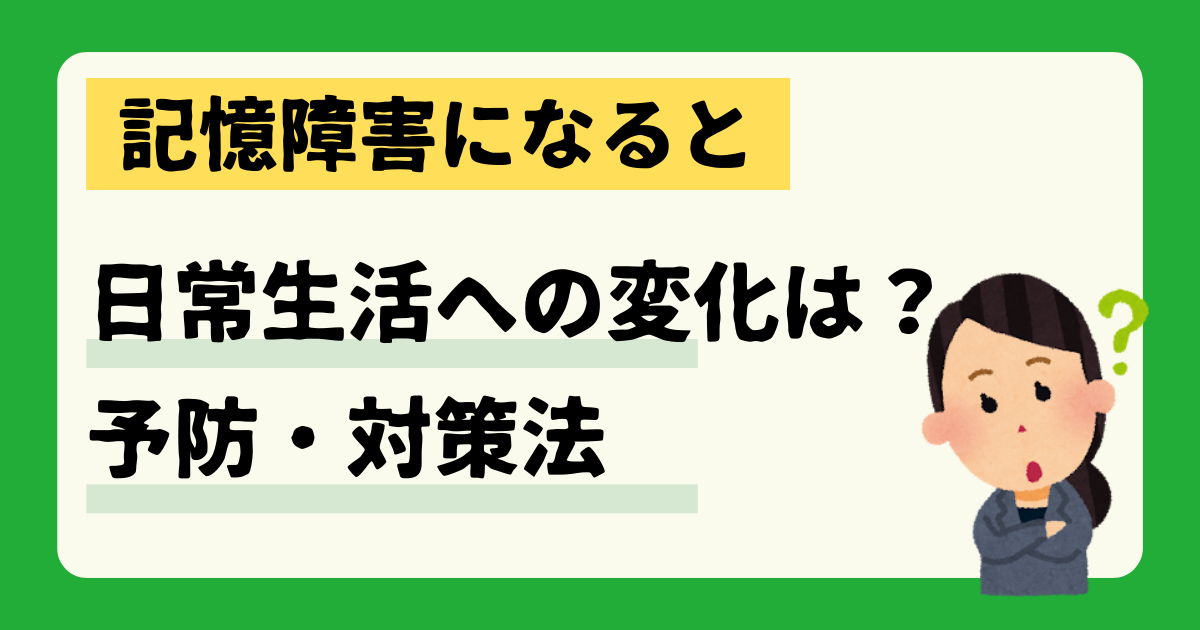
新しいことを覚えるのが難しくなったり、過去に体験したできごとを思い出せなくなる「記憶障害」は、単なる「物忘れ」とは違って脳の機能障害です。記憶障害になると、日常生活に大きな影響があります。本記事では記憶障害になったときの日常生活の変化や、記憶障害の予防法、記憶障害になった時の対策について解説します。
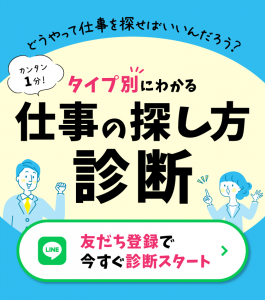
目次
記憶障害とは
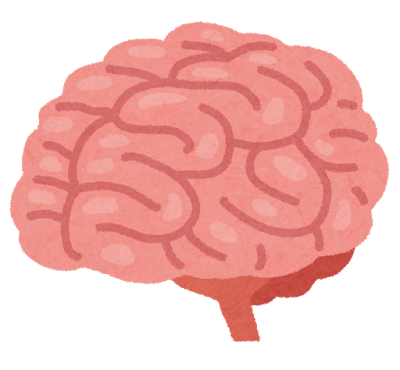 記憶とは、過去の経験や覚えた情報(記銘)を脳に保管(保持)して、それを後から思い出す(想起)機能のことです。
記憶とは、過去の経験や覚えた情報(記銘)を脳に保管(保持)して、それを後から思い出す(想起)機能のことです。
記憶は大きく分けると、「長期記憶」と「短期記憶」に分類されます。新しい経験は、脳の海馬で一時的に保存された後、陳述記憶(言葉の意味やエピソードとして意識化できる記憶)、非陳述記憶(自転車に乗る方法など意識として想起できない記憶)が選択されて大脳新皮質に「長期記憶」として保存されます。このほかの不要な記憶は、「短期記憶」として海馬で消去される仕組みになっています。
「記憶障害」は、何らかの原因で脳機能が不全となり「物事が思い出せない」「覚えられない」状態になります。
記憶障害の原因
 記憶障害の主な原因には、「加齢に伴う記憶力の低下」「軽度認知障害」「認知症」「うつ病」があります。
記憶障害の主な原因には、「加齢に伴う記憶力の低下」「軽度認知障害」「認知症」「うつ病」があります。
加齢に伴う記憶力の低下
加齢に伴う記憶力の低下は、年を取ると誰でも起こる脳機能のわずかな低下のことで、最も一般的な記憶障害の原因です。
軽度認知障害
軽度認知障害とは、日常生活に影響を及ぼすほど重度ではない認知機能の障害を指します。ほとんどの場合は記憶障害が最も目立つ症状です。
認知症
認知症は、軽度認知症より深刻な認知機能の衰えです。認知症の方は、できごとの細部だけでなく、できごと自体を忘れてしまいます。認知症の初期の段階では、本人が記憶障害を自覚していることがあります。しかし、加齢に伴う記憶力の低下とは異なり、認知症が進行すると記憶障害を認識できなくなり、記憶障害を否定することがあります。
うつ病
うつ病は、認知症による記憶障害に似た症状(仮性認知症)を引き起こすことがあります。また、認知症もうつ病の原因になることがあります。
他にも、甲状腺機能低下症・正常圧水頭症・硬膜下血腫・ビタミンB12欠乏症・頭部の外傷・脳の感染症・HIV感染症・脳腫瘍・特定の薬物(アルコールなど)の過剰摂取などが原因となることがあります。
「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
→【LINEおともだち追加】で診断してみる
記憶障害の種類と症状と日常生活への変化
記憶障害にはいくつかの種類があり、それぞれ症状が異なります。
短期記憶障害
短期記憶障害は、数十秒から数時間など短い時間で起こったできごとを記憶する機能が低下することです。日常生活では、「1時間前にしていたことが思い出せない」「今日の日付や曜日がわからない」「物を置いた場所をすぐに忘れる」といった症状が現れます。
長期記憶障害
長期記憶障害は、長期的に記憶していた記憶に障害が生じます。具体的な症状としては、「自分の通った学校の名前が思い出せない」「自分が結婚しているのか思い出せない」などです。
エピソード記憶障害
エピソード記憶障害は、自分が体験した出来事(エピソード)を、きちんと思い出せない状態をいいます。一定範囲内のできごとが全体的に思い出せないケースや、断片的な記憶はあっても、それがどんな内容だったのか分からないケースもあります。
意味記憶の障害
意味記憶の障害は、動物や植物の名前、自然現象の名称、歴史上の人物など、ものや言葉の意味を忘れてしまう障害です。日常茶飯事では、「あれ」や「それ」などの表現が多くなって、意思疎通が難しくなります。
手続き記憶の障害
手続き記憶の障害は、繰り返し学習や練習を行って身に付けた技術や自然と体が覚えている動作などに障害が生じます。日常生活では、料理の作り方や包丁の切り方、洗濯物のたたみ方、自転車の乗り方など、考えなくても自然にできていたことができなくなります。
記憶障害の予防と対策
高齢者に多い記憶障害の原因は、軽度認知症と認知症です。「これをやれば軽度認知症や認知症にならない」という絶対的な予防策はありませんが、食事や運動、知的刺激は認知症を予防する重要な要素と言われています。
食事
認知症の予防に大切なのは脳の健康を保つことです。生活習慣病の改善と食事からの老化を予防しましょう。たんぱく質や脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど栄養バランスが良い食事は、脳に必要な栄養素を補うことになります。また、食べすぎや間食を控えて、カロリーや糖分、塩分の摂り過ぎに注意しましょう。
運動
ウォーキングやサイクリング、水中歩行などの有酸素運動は、認知症の予防に効果があるとされており、週に3〜5回は30分程度の運動を行うことが良いとされています。
知的刺激
読書、料理、旅行、音楽、ゲーム、パズルなどの知的活動を行うほど、認知症の発症リスクが減少するとの研究があります。
また、社会活動に参加することも脳にさまざまな刺激を与えるため、認知症を予防する効果が期待できます。サロンやデイサービスで他の人と会話する、ボランティアに参加するなど、人と関わって社会の中での役割を持つことは、認知症の予防につながる大切な対策です。
専門医に診てもらう
軽度認知症や認知症によって記憶障害になったのでは?と思われる症状に気づいたら、一人で悩まずに専門医などに相談しましょう。認知症を治療できる薬はありませんが、進行を遅らせる薬はあります。
「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
→【LINEおともだち追加】で診断してみる
記憶障害への対応や支援
家族や知人が記憶障害になった場合、周囲の人にできる対応や支援を紹介します。
記憶障害になった本人に安心してもらう
記憶障害によって本人の認識と事実にズレが生じてくると、つい本人の言動を訂正してしまいがちですが、本人にとっては間違っているという自覚がないため、自分の言動が否定されると不安や怒りの感情を抱きがちです。そのため間違っていても、周囲の人が本人の言動を否定せずに合わせることが大切です。
環境を整える
記憶に頼らなくて良い環境にすると、記憶障害の影響を最小限に抑えることができます。例えば、物の置き場所を変えないようにする、毎日のスケジュールをパターン化するなどです。
また、ストレスを管理するのも重要です。ストレスは認知症を進行させます。しかし、本人がストレスを管理するのは非常に困難です。本人が安心して生活できるように、周囲の人がサポートしてあげましょう。
ツールを活用する
メモやチェックリスト、カレンダー、アラームなどを活用して、日課や予定、注意事項などを確認しやすくする工夫をしてみましょう。また、新しいことを覚える時には、聴覚だけでなく視覚や触覚も合わせて使って覚えると効果的です。声に出して書いて覚える習慣をつけましょう。