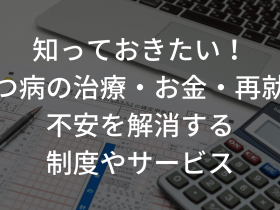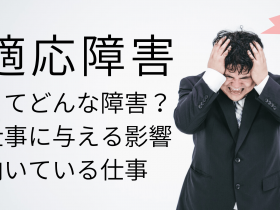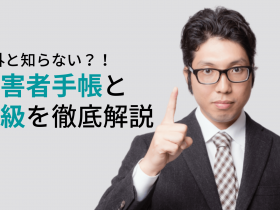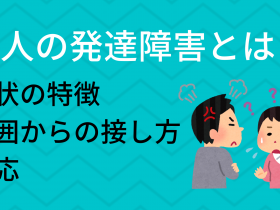文字が読めないのは病気? ディスレクシアと失読症の違い
更新日:2025年10月29日
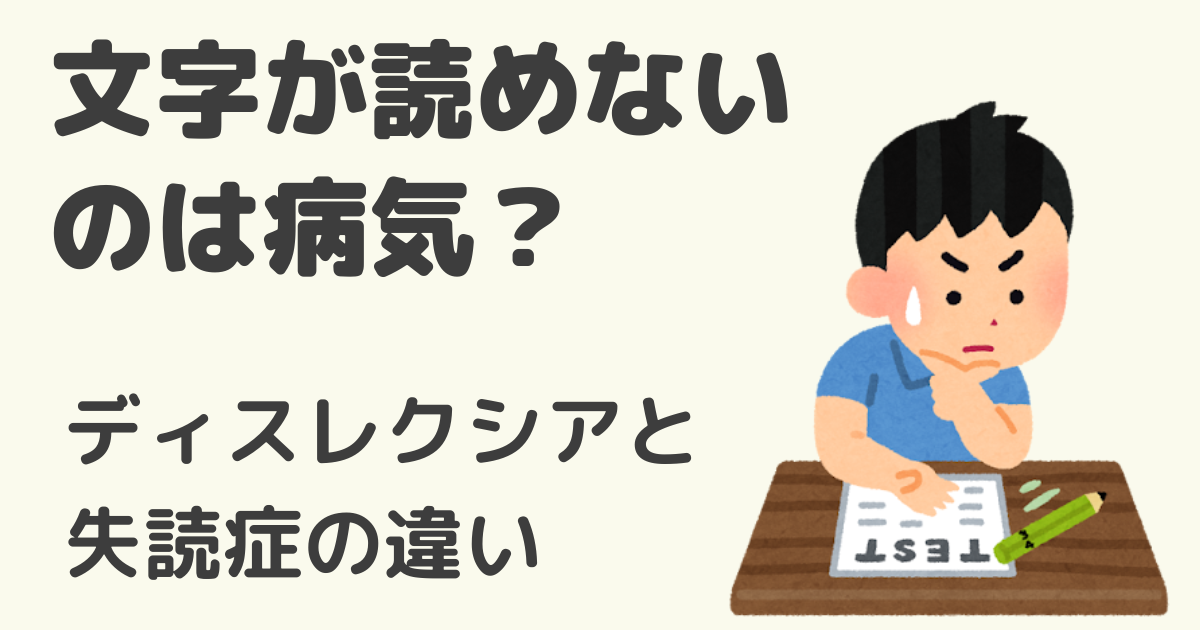
文字や文章が読めないという症状は、限局性学習症(SLD))/学習障害(LD)で見られる特徴です。限局性学習症(SLD)/学習障害(LD)は発達障害のひとつで、生まれつきの脳の発達の違いが原因のため、ほとんどの場合は子供の頃に症状が現れます。一方で、脳が損傷することで後天的に文字が読めなくなる障害もあります。本記事では、読字障害(ディスレクシア)と失読症について、症状や原因、困ることへの対策法、利用できる支援などを紹介します。
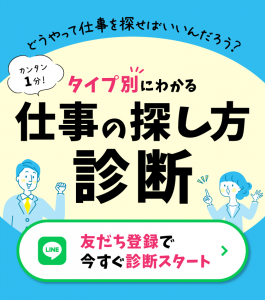
目次
文字が読めないときに考えられる病気
大人になって文字が読めない原因としては、「ディスレクシア(読字障害)」や、脳が損傷することで後天的に読み書きが困難になる「失読症」が考えられます。
ディスレクシアの特徴と原因
ディスレクシアは、限局性学習症(SLD)/学習障害(LD)のひとつのタイプです。限局性学習症(SLD)には、大きく読字障害(ディスレクシア)・書字表出障害(ディスグラフィア)・算数障害(ディスカリキュリア)の3つのタイプがあります。
このうち、読字障害(ディスレクシア)は、全体的な知的発達には遅れはないのに、文字の読み書きに困難が生じる発達障害です。原因について明確には分かっていませんが、脳の発達に何らかの偏りがあると考えられています。読字障害(ディスレクシア)の一般的な特徴には、以下のようなものがあります。
●読字障害
・読み飛ばしたり、文末を自分で変えて読むことがある
・語や文章を途中で区切って読むことがある
・文字の間隔や行間が狭いと読みづらいと感じる
・どこを読んでいるか文字を追いかけることが難しい
・文字や本を読むと疲れやすい
・読んでいるところを確認するように指で押さえながら読む
●書字障害
・促音(小さい「っ」)、撥音(ん)、二重母音など特殊音節を書くのが苦手
・「わ」と「は」、「お」と「を」のように同じ発音の文字を間違える
・「め」と「ぬ」、「わ」と「ね」のように似ている文字を間違える
・画数の多い漢字を間違えることが多い
失読症の特徴と原因
失読症は、脳の特定の部位が損傷された後に発生する読み書きの障害です。主に成人に発生します。失読症の症状は、人によってそれぞれ異なりますが、一般的には読むのに時間がかかる、文字や文章を理解するのが難しいというような特徴があります。
失読症を発症する原因は、主に脳の損傷です。特に、左半球の言語を処理する領域を損傷した場合に発症します。主な要因は、脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍、感染症後の炎症などによるものです。
ディスレクシアと失読症の違いと共通する症状
ディスレクシアと失読症は、どちらも読み書きに困難を伴う障害ですが、原因と発症のタイミングに大きな違いがあります。
ディスレクシアは、先天的な学習障害(発達障害)で脳の発達に偏りがあり、その特性から文字を識別したり理解することが困難となります。これに対して、失読症は脳の損傷、脳卒中や外傷などが原因で、後天的に発症して読書能力が損なわれます。このように原因や発症するタイミングは異なりますが、症状が似ているため対処法や治療法は、同じ場合が多くあります。
大人になってから気づく学習障害
ディスレクシアなどの限局性学習症(SLD)/学習障害(LD)は、生まれつきみられる脳の発達の偏りが原因のため、大人になってから発症することはありません。多くの場合は子どもの頃に特性が現れて気づきますが、本人も家族も気づかずに大人になることがあります。
子どもの頃には、周囲から単なる苦手と思われていたことが、社会人になって仕事を通じて読み書きに困難を感じて、限局性学習症(SLD)/学習障害(LD)だと判明するケースや、発達障害について広く知られるなったことで気づくケースがあります。
ディスレクシアや失読症が仕事や生活に与える支障
ディスレクシアや失読症の方は、その症状によって仕事や日常生活において次のような困難を感じるケースがあります。
仕事面で困ること
・資料やマニュアルなどを読んでも理解するのが難しい。
・文字や文章を理解するのが難しいため、資料の作成やメールの返信に時間がかかる。
・資料を読んでもすぐに忘れてしまう。
移動時に困ること
・地図や路線図、標識、案内看板などが理解できない。
・電車やバスに乗る時に、書かれている行き先がすぐに読めない。
・乗車しても、降車する駅やバス停が読めずに降りれない。
日常の買い物に関して
・商品名や商品の説明が読めないため、違う商品を購入してしまう。
・無人レジで表示される文字が理解できない。
ディスレクシアや失読症で困ることへの対処法
ディスレクシアや失読症の方が、仕事や日常生活で困ることへの対処法を紹介します。
ツールやソフトウェアを活用する
文字を読むのが困難な方は、オーディオブックや音声認識ソフトウェアの使用がおすすめです。これらのツールは、文字を視覚ではなく聴覚で理解することに役立ちます。また、文字を書くのが困難でメモが取れない方は、ボイスレコーダーを使うと良いでしょう。最近のボイスレコーダーの中には、文字起こしの機能がついている商品もあります。
文章を区切る、ふりがなを振る
ディスレクシアや失読症の方は、文章のどこを読んでるのか分からなくなったり、文字の間隔や行間が狭いと読みづらいと感じることがあります。適度な長さで文章を区切ることで読みやすくなります。
また、漢字にふりがなを振ることでも文章が読みやすくなります。文章作成ソフトのふりがな機能を活用しましょう。
ディスレクシアの治療
ディスレクシアなどの限局性学習症(SLD)/学習障害(LD)には、根本的な治療法はありません。そのため、対処療法としてトレーニングを行って、障害の特性とうまく付き合いながら、生きていく方法を身につけることが大切です。
ディスレクシアの対処療法としては、ビジョントレーニングという視覚機能を高めるためのトレーニングが行われるケースがあります。ビジョントレーニングは、眼球運動や視覚情報の処理、目と体の協応動作などを鍛えるトレーニングで、発達障害の改善に活用されています。視覚機能を高めるトレーニングは、大きく分けて入力機能・情報処理機能・出力機能の3つに分けて行われます。
ディスレクシアは、読み書きが困難なことから周囲からの誤解を受けて、読み書きに対する拒否感や強い劣等感が生まれることがあります。さらにひどい時には、うつ病を引き起こしてしまうことがあります。
ディスレクシアによって併発したうつ病の治療には、TMS治療(経頭蓋磁気刺激)が行われることがあります。TMS治療(経頭蓋磁気刺激)は、磁気の刺激によって脳の特定部位を活性化させ、脳血流を増加させて低下した脳機能を元に戻す治療法です。
失読症の治療
ディスレクシアや失読症の方が利用できる支援
ディスレクシアや失読症の方が、その症状によって日常生活や仕事で困った時には次にあげる支援やサポートを利用できます。
障害者雇用制度の活用
障害者雇用促進法では、一定以上の規模の企業に障害者を雇用することを義務付けており、従業員に対する障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合を「法定雇用率」以上にしなければなりません。
障害者雇用制度を利用すると、資料やマニュアルなどを読んでも理解するのが難しいといったディスレクシアや失読症の方の困難に対して、職場のサポートや配慮が期待できます。
また、障害者雇用制度は一般の求人より就職しやすい傾向があるというメリットもあります。一方で、募集される職種や業務内容が少ないといったデメリットもあります。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、地域のさまざまな機関と連携して、障害者の仕事と生活を一体的に支援する公的機関です。
就労面の支援では、就業に関する相談支援、障害の特性を踏まえた雇用管理について事業所に対して助言する、関係機関との連絡調整が行われています。生活面の支援は、日常生活や地域生活に関する助言と関係機関との連絡調整です。
就労移行支援事業所
就職移行支援は、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつで、一般企業への就職を目指す障害者に対し、働くために必要な知識やスキルを身につけるトレーニングや就職後も安定して働けるようにサポートを行っています。
就労移行支援は通所型のサービスのため、事業所へ定期的に通うことで、就職した時と同じような生活習慣が身につけられるメリットがあります。また、訓練によって自分の強みや弱みを把握でき、最大2年間にわたって通所し、支援員や他の利用者と一緒にプログラムを行うため、コミュニケーション能力や協調性が身につくといったメリットもあります。
障害に特化したコース別の就労移行支援サービス
「atGP(アットジーピー)ジョブトレ」は、障害者の転職サービス業界 No.1の実績を誇る「atGP」が運営する就労移行支援サービスです。
「atGPジョブトレ」は、うつ病・発達障害・統合失調症・聴覚障害・難病の5つのコース制で、専任のスタッフが、個別面談を通じて障害の理解と対処法を考えるので、自分の障害と上手く付き合いながら働き続けるためのスキルが身につきます。
障害者の就職・転職に詳しいキャリアプランナーに相談しながら就職活動を進めることができる「atGPエージェント」や障害者雇用枠での求人を自分で探したりスカウトを受けることができる「atGP転職」も併用することで、就職の可能性が広がります。