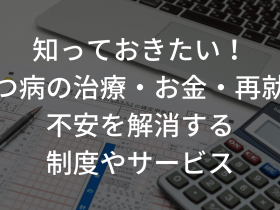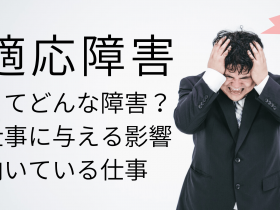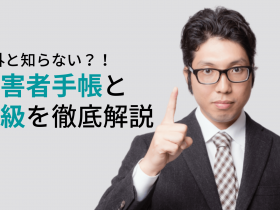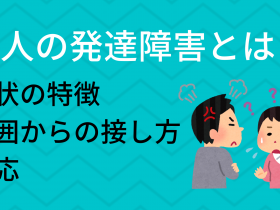瞬きが多いのは病気? チック症や目の不調との関係
更新日:2025年10月29日
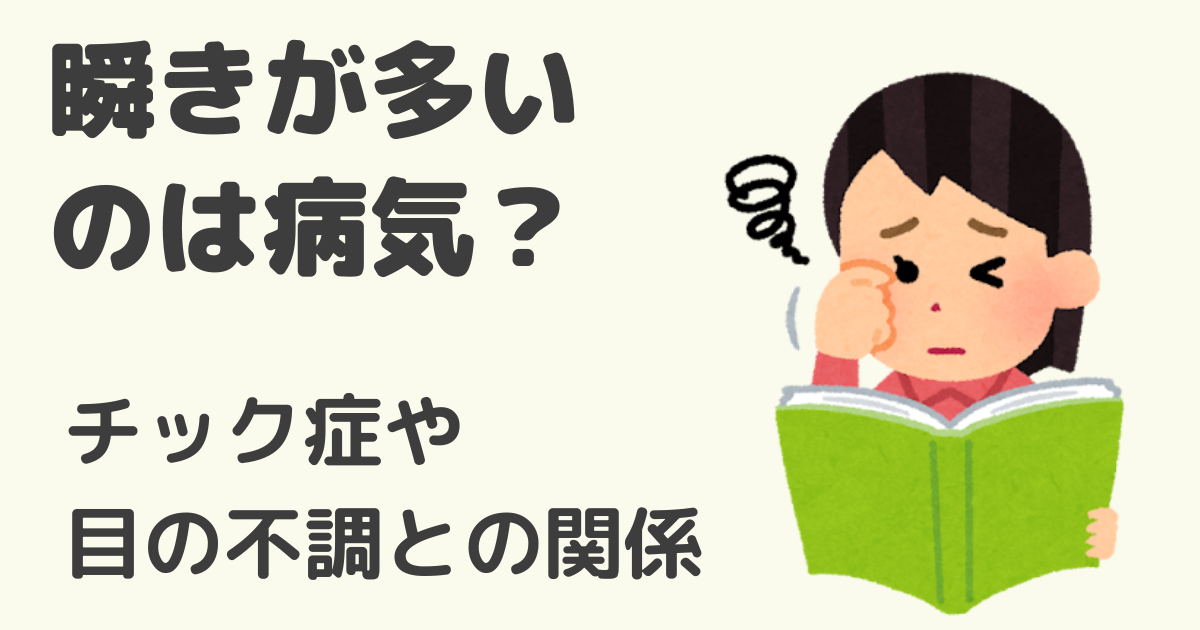
自分では意識していないのに、不自然に瞬きが多くなる。ひょっとするとその原因は病気かもしれません。本記事では大人の方が、瞬きが多くなる病気の中でも、特にチック症について、症状や治療法、自分でできる対策などを紹介します。
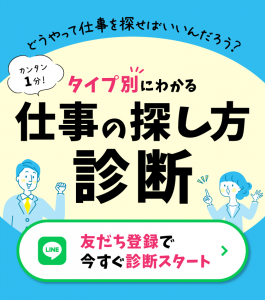
目次
大人の瞬きが多くなる病気
眩しい時や緊張した時など、瞬きが多くなることがあります。このように一時的に瞬きが多くなる状態は問題ありませんが、頻繁に起こる場合には眼の病気などが原因となっている可能性があります。
眼に関する病気
次のような眼の病気が原因で瞬きが多くなることがあります。
●ドライアイ
ドライアイは、涙の分泌量が不足したり質が低下することによって、涙が眼の表面に行き渡らなくなって、目の乾きや不快感などを引き起こす病気で、時には眼の角膜が損傷することもあります。目の乾きや目のかすみ、充血といった不快感から、瞬きが多くなります。
●睫毛内反
睫毛内反(しょうもうないはん)は、まつ毛が眼球の方を向いてしまい、眼に接触している状態で逆さまつ毛とも呼ばれます。まつ先が眼球に触れることで、異物感、涙が多くなる、充血や痛み、瞬きの増加などの症状を引き起こします。
●アレルギー結膜炎
アレルギー結膜炎は、花粉やハウスダスト、ダニ、ペットの毛などが眼の表面に付着して、アレルギー反応を起こし、眼のかゆみ、充血、異物感などを引き起こす病気です。アレルギー結膜炎になると、眼の表面の角膜に炎症が起きて、瞬きが多くなります。
●角膜びらん
角膜びらんは、外傷やコンタクトレンズの不適切な使用、ドライアイなどが原因で発症する眼の病気です。角膜の最も外側の層である角膜上皮が、浅く傷ついたり剥がれたりする状態で、強い痛み、涙の増加、充血、異物感といった症状を引き起こし、瞬きが多くなります。
眼精疲労
眼精疲労は、疲れ目が進行した状態で、眼の痛み、眼のぼやけやかすみ、まぶしさ、充血などの症状に加えて、頭痛、肩こり、吐き気など全身に症状が現れて、睡眠や休息をとっても回復しない状態です。眼精疲労によって、瞬きが多くなることがあります。
屈折異常
屈折異常は、眼に入った光が網膜上で正しく結ばない状態です。屈折異常には、大きく分けて、近視・遠視・乱視があります。ピントが合わないことから、かすみ目や視界のぼやけなどの症状が起きます。眼鏡やコンタクトレンズによって適切な矯正がされていないと、見えにくさから瞬きが多くなることがあります。
大人のチック症
チック症は、本人の意思とは関係なく運動や発声を繰り返してしまう病気です。チック症の症状は、運動チックと音声チックに大きく分けられます。
運動チックでよく見られるのは、瞬きをする、肩をすくめる、顔をしかめる、首を振るなどです。音声チックでは、とくに意味がない発声や呼吸音が聞かれます。また、特定の言葉を繰り返したり、汚い言葉を発することもあります。
幼少期から小児期にかけて発症する病気で、大人のチック症は子供の頃から慢性的に続くものや、大人になってから再発したり悪化するケースがほとんどです。
大人のチック症と似ている症状が現れるものに、ADHDなどの発達障害、強迫症、不安症、うつ病などの精神疾患、てんかんなどの脳神経疾患があります。
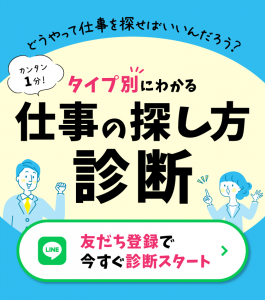
大人のチック症で困ること
チック症は、本人の意思とは関係なく身体が動いたり声が出るため、日常生活や仕事で困ることが多くあります。大人のチック症で、困りがちなことには次のようなものがあります。
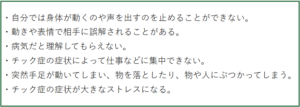
大人のチック症の診断と治療
チック症は、幼少期から小児期にかけて発症する病気で、大人になってから発症することは稀です。しかし、子供の頃から継続していたり、大人になって再発するケースがあります。
受診先と診断
チック症かもしれないと思ったら、大人の場合精神科や心療内科などの専門医を受診します。医師は、子供の頃にチック症が発症しているかどうかを確認し、大人になってから症状が現れた場合には、他の疾患の可能性などもチェックします。
診断は、アメリカ精神医学会の診断基準であるDSM-5など、国際的に用いられている診断基準に基づいて行われます。
大人のチック症の治療法
チック症の治療は、主に「薬物療法」「認知行動療法」が行われます。
●薬物療法
チック症の症状が重く、日常生活や仕事に大きな支障をきたしている場合に、症状を抑えるために薬物療法を行うことがあります。ドーパミン受容体拮抗薬(抗精神病薬)は、脳内のドーパミンの働きを抑えることで、チック症の症状を軽減すると考えられています。高血圧の薬でもあるクロニジンは、チック症に伴うことがある不安感や多動などにも効果が見込まれます。
●認知行動療法
認知行動療法は、症状を引き起こす考え方や行動の癖を、治療を通して自身でコントロールできるようにする心理的な治療方法です。チック症の治療には、主に習慣逆転法(ハビットリバーサル)と呼ばれる体系的なトレーニングによって、チック症の症状を自分で管理する能力を高める方法が用いられます。
大人のチック症の方が自分でできる対策
大人のチック症の方が、治療以外に自分でできる対策を紹介します。
周囲の人に理解してもらう
チック症について知らない人が多いので、まずは周囲の人にチック症について理解してもらいましょう。突然の身体の動きや発声が、本人の意思とは無関係に出てしまうことを理解してもらうことで、症状が出てしまうかもしれないという不安や緊張を軽くすることができます。職場では、上司や同僚に理解してもらうことで、配慮やサポートを受けやすくなります。
安心できる場所を確保する
仕事中は、ストレスや不安を感じることが多いため、チック症の症状が悪化するケースがあります。症状が出て苦痛に感じる場合には、一人になることができる場所で、気持ちを落ち着けましょう。職場や職場の近くに、あまり人が来ない安心できる場所を確保しておくとよいでしょう。
障害者雇用枠での転職
チック症は発達障害のひとつです。今の職場で働き続けるのに困難さや苦痛を感じている場合には、障害雇用枠での転職を検討するのもひとつの方法です。
「atGP(アットジーピー)」は、障害者の転職サービス業界 No.1の求人転職情報・雇用支援サービスです。障害雇用枠での求人情報が多数あり、障害配慮や障害者の雇用実績、職種、業種、エリアなどの条件で探すことができます。
また、「atGP(アットジーピー)」が運営する就労移行支援サービス「atGP(アットジーピー)ジョブトレ」は、うつ病・発達障害・統合失調症・聴覚障害・難病の5つのコース制で、自分の障害と向き合いながら働き続けるスキルが身につきます。