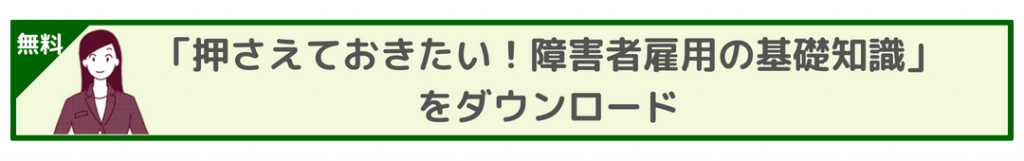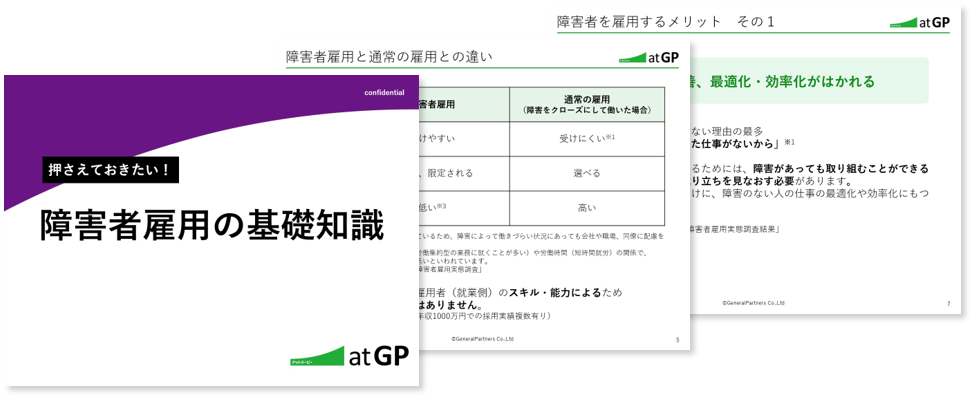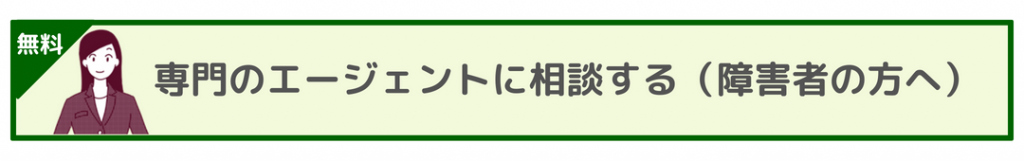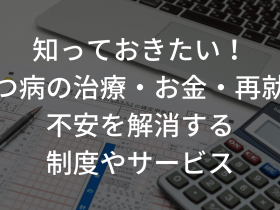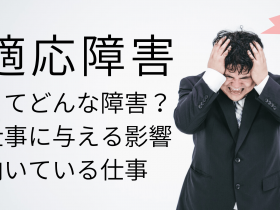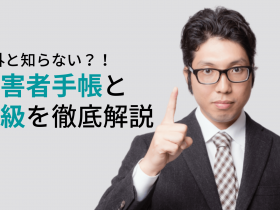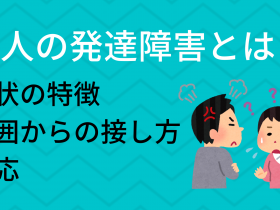令和元年の障害者雇用促進法の改正ポイントとは?
更新日:2023年11月13日
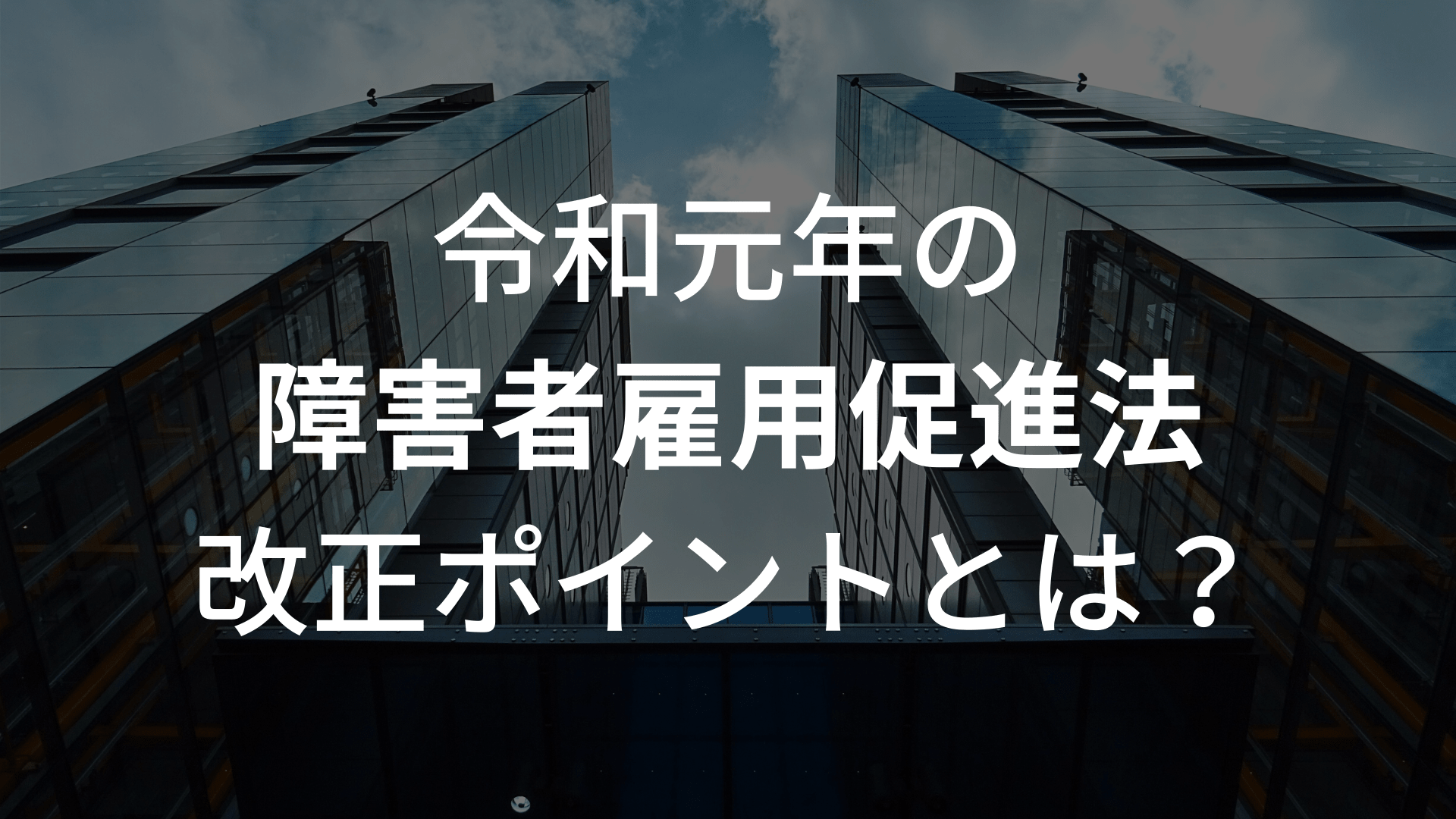
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下、「改正障害者雇用促進法」とします)が令和元年6月14日に公布されました。 本稿ではどんな内容が改正されたかについてポイントをかいつまんで解説したいと思います。
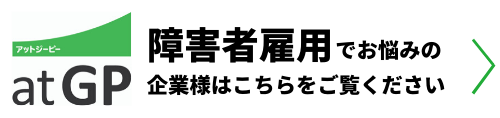
目次
ポイント1:公的機関の障害者雇用水増し問題の再発防止策が盛り込まれた
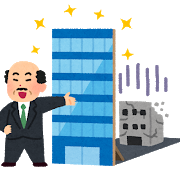
2018年8月に中央省庁における障害者雇用の水増し問題が発覚(のちに地方公共団体でもこの問題が拡大していきました)し、それを受けて再発防止策としての内容を盛り込んだ改正障害者雇用促進法が2019年6月14日に公布されました。
国および地方公共団体における障害者の雇用状況について、的確な把握等に関する措置を講ずることとする内容が盛り込まれており、障害者雇用水増し問題に対応したものとなっています。
この改正法では、公的機関(国・地方公共団体)は、障害職員が自身の能力を有効に発揮し仕事で活躍するための取り組みを「推進障害者活躍推進計画」に作成し、公表することを義務付けています。
また、公的機関(国・地方公共団体)に対して、障害職員の任免状況について毎年公表することも義務付けました。
これまで公的機関で雇用した職員が障害者であるかどうかについて、確認する手段があいまいだったことも雇用水増しにつながる一因だったわけですが、改正法では明確に「障害の確認に使う書類は、厚労省が定めたものをつかうこと」と定められました。
障害者雇用にまつわるメリット・デメリットをはじめ、最低限知っておきたい基礎知識をご紹介する資料がダウンロードできます。
この資料でわかること
・障害者雇用とは?
・障害者を雇用するメリット
・障害者を雇用しないデメリット
・障害者雇用が進まない企業が抱える課題
・課題を解消するポイント
・押さえておくべき障害者雇用の法律・制度
ポイント2:20時間未満の短時間労働に特例給付金の支給が創設された
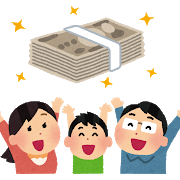
加えて、民間の事業主に対する措置として、
短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満(下限は週10時間)の労働者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みが創設されました。
なお、この措置は令和2年(2020年)4月1日からの施行とされています。
支給要件・額は以下の通りとなっています。
| 事業主区分 | 支給対象の雇用障害者 | 支給額 注1 | 支給上限人数 注2 |
| 100人超(納付金対象) | 週10時間以上20時間未満 | 7,000円/人月(≒調整金@27,000円×1/4) | 週20時間以上の雇用障害者数(人月) |
| 100人以下(納付金対象外) | 〃 | 5,000円/人月(≒報奨金@21,000円×1/4) | 〃 |
(注1)支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出する。
(注2)支給上限人数の算定においては、重度のダブルカウント及び短時間のハーフカウントを行う。
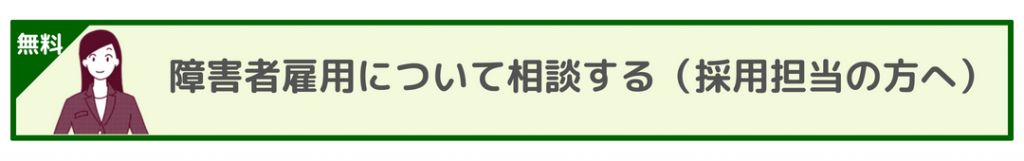
「障害者雇用の基礎知識」資料が無料ダウンロードできます
障害者雇用については、「障害者雇用促進法」という法律で義務付けられていますが、障害者雇用促進法には、他にも障害者差別の禁止や合理的配慮の提供の義務などが定められています。
障害者雇用にまつわるメリット・デメリットをはじめ、最低限知っておきたい基礎知識をご紹介します。
この資料でわかること
・障害者雇用とは?
・障害者を雇用するメリット
・障害者を雇用しないデメリット
・障害者雇用が進まない企業が抱える課題
・課題を解消するポイント
・押さえておくべき障害者雇用の法律・制度
▼サンプル
ポイント3:障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度の創設

中小企業での障害者雇用のとりくみが停滞しているという状況を鑑み、社会的な関心を喚起し、先進的な取組を進めている事業主が社会的なメリットを受けることができるよう、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度を創設することになりました。
この認定制度を活用し、自社や自社製品の広報やブランディングに役立てることが期待できるとともに、自社の働きやすさをアピールすることで、障害の有無にかかわらず採用・人材確保の円滑化にも寄与できるものと思われます。
以上、大まかな改正ポイントとして3点取り上げました。
公的機関の雇用障害者の不適切計上の再発防止、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会の確保、中小企業における障害者雇用の促進、という課題に対して今回の法改正がなされたという意味においては、一定程度の評価はできるのではないかと思われます。