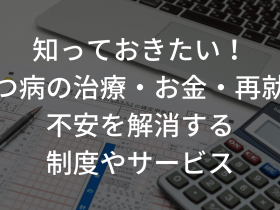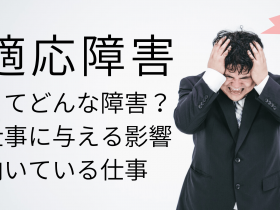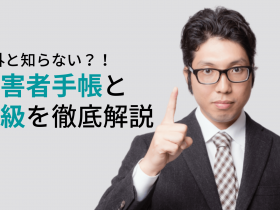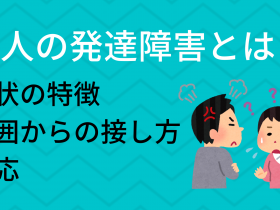職業リハビリテーション(通称:職リハ)って何?その内容を詳しく解説!
更新日:2022年03月31日
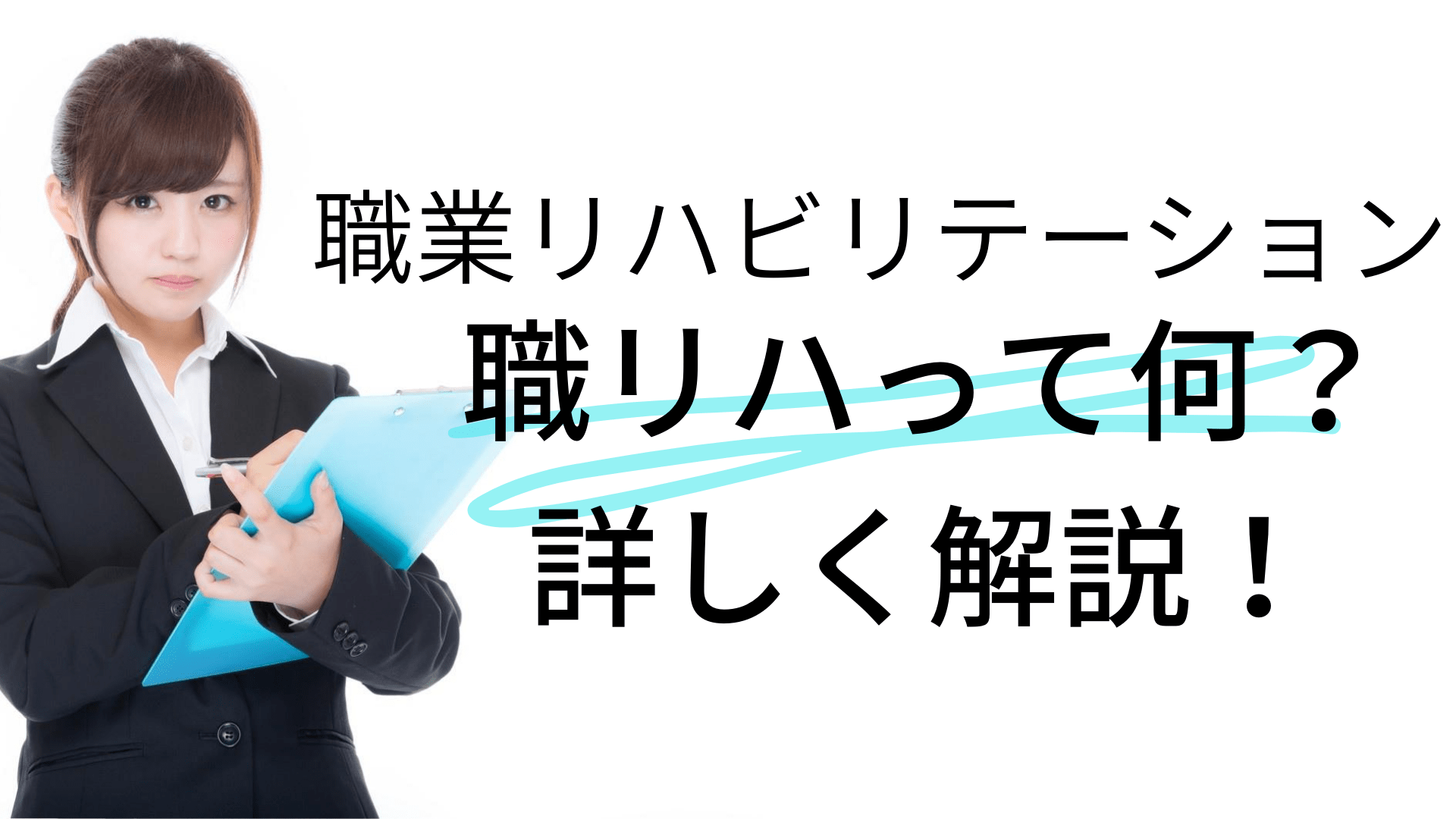
障害や重い病気を抱える人が、社会に出るにあたって必要な訓練を行うことができる職業リハビリテーションという制度があります。この制度を利用して、社会に出て働くために必要なスキルを身につけ、就業に関してのサポートを得ることで、障害や重い病気を抱えていても社会に出て働くことが可能になります。ここでは、その職業リハビリテーション(職リハ)について解説していきます。

目次
職業リハビリテーション(職リハ)とは

職業リハビリテーションとは、国際労働機関(ILO)により「職業リハビリテーションとは、継続的かつ総合的リハビリテーション過程のうち、障害者が適当な職業の場を得、かつそれを継続できるようにすることが出来るようにするための職業サービス。例えば職業指導、職業訓練、および選択的職業紹介を提供する部分をいう」と定義されています。
さらにILOは1983年に「障害者のリハビリテーションに関する条約」の第159号条約において「職業リハビリテーションの目的は、障害者が適当な雇用につき、それを継続し、かつ、それにおいて向上することが出来るようにすること及びそれにより障害者の社会への統合または再統合を促進することにある」と規定しました。
また、日本では障害者雇用促進法の第八条において職業リハビリテーションは、「職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適正、職業訓練等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されるものでなければならない」と定められています。
このような目的を持って行われる職業リハビリテーションの内容は、職業評価、職業指導、職業準備訓練と職業訓練、職業紹介、保護雇用といった内容があります。
このそれぞれの内容は後ほど詳しく解説しますが、このようなサービスの提供を受けることにより、障害者や重い病気を抱える人が、社会参加を行い、職業に就き、安定して働き続けることが出来るようにサポート行うことが、職業リハビリテーションの内容となっています。
職業リハビリテーションの対象者ってどんな人?
職業リハビリテーションの対象となる人は、
・身体障害者
・重度身体障害者
・知的障害者
・重度知的障害者
・発達障害を含む精神障害者
・その他心身の機能障害者
です。
その他心身の機能障害者とは、精神疾患(発達障害を含む)や高次脳機能障害、難病がある人のうち、障害者手帳を持っていない人のことを言います。
これらの人々のなかで、採用側の企業における障害者雇用率の算定の対象となるのは、障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人のみとなっていますが、これらの手帳を持っていない人でも、職業リハビリテーションを受けることが可能です。
しかし、実際には職業リハビリテーションを行う施設によってサービスを受けることができる対象者が決められています。
そのため、自分が職業リハビリテーションを受けようと思った場合には、自分の障害や病気に適した職業リハビリテーション実施施設を探す必要があります。
職業リハビリテーションのサービスとプログラムにはどのようなものがある?

職業リハビリテーションの内容は、職業評価、職業指導、職業準備訓練と職業訓練、職業紹介、保護雇用といった内容があることは前述しました。
ここではその内容について詳しく解説していきます。
職業評価
職業評価とは、職業リハビリテーションを行う機関に入所する前に、入所後の職業訓練を的確なものにするために身体的側面、学力等の基礎の能力の側面、医学的側面、社会的側面、職業的側面について整理することです。
この職業評価を行うことにより、その後に実施される職業訓練の受講に必要となる基礎学力や適正、健康状態、就労に関する要望などを確認し総合的にその機関への入所が適正であるかが判断されます。
この職業評価の結果をもとに支援計画が作成されます。
職業指導
職業指導とは、職業評価によって得られた情報により本人の資質に合った訓練を行うことを言います。
初めのうちは自分の体調のコントロールする方法を体得することから始まることが一般的ですが、プログラムが進むにつれて仕事で必要となるスキルを身につけるための訓練へと徐々に移行していきます。
職業紹介
職業評価と職業訓練を受け、自分の持つ障害や病気の特性を理解した上で就労に必要なスキルを習得した後に、自分に合った職業を紹介してもらうことが可能になります。
自分の適性に合った仕事を探すとともに、面接のシミュレーションや企業側に提出する必要書類の添削を受けることも可能です。
保護雇用
保護雇用とは、一定の特別な配慮のもとで企業に雇用されることを言います。障害や病気を持っている人にとって、企業側にハード面またはソフト面、またはその両方の配慮をしてもらいながら働くことは、長く働き続けるためにとても重要なことです。このような保護雇用の環境下で、特別な配慮やサポートを受けながら長期にわたり就業できるようにすることが、職業リハビリテーションの最終的な目標となります。
職業リハビリテーションの実施機関はどこ?

職業リハビリテーションを行っている機関には、どのようなものがあるのでしょうか。以下に職業リハビリテーションの実施機関を紹介していきます。
公共職業安定所
就職を希望している障害者や重い病気を抱える人の求職者登録を行い、専門の職員および職業相談員がケースワーク方式により障害の種類や程度に応じてきめ細かな職業相談や紹介、職場定着支援を行ってくれます。
就職後のアフターケアまで一貫して利用することができます。
障害者職業センター
この障害者職業センターの中には障害者職業センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターの3つの種類があります。
このうち一般の障害や重い病気を抱える人が利用できるのは、広域障害者職業センターと地域障害者就業センターです。
広域障害者就業センターでは障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した、系統的な職業リハビリテーションが実施されています。
一方、地域障害者就業センターでは、障害者に対して職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応応援助などの専門的なリハビリテーションを受けることができ、また、企業側にも雇用管理に対するアドバイス等を実施しています。
障害者雇用支援センター
障害者雇用支援センターでは、就職が特に困難と思われる障害者に対して職業準備訓練を中心とした雇用支援を実施しています。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターにおいては、障害者の身近な地域において雇用、保健福祉、教育等の関連機関と連携して、就業面や生活面における一体的な相談支援を行っています。
障害者職業能力開発校
障害者職業能力開発校では、訓練科目や訓練指導方法に特別な配慮を加え、障害の特性に応じた職業訓練や技術革新の進展などに応じた在職者訓練などを行っています。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所では、職業リハビリテーションで受けることができるサービスを一貫して提供しています。
そのため、職業リハビリテーションの段階に応じて相談や通所先を変更する必要がありません。
職業リハビリテーションのサービスを受ける場合には、この機関が一番向いていると言えます。
まとめ
ここまで、職業リハビリテーションとはどのような物かということ、職業リハビリテーションの対象となる人とその内容、職業リハビリテーションを実施している機関について解説してきました。
障害や重い病気を抱える人が利用することが出来る職業リハビリテーションについてお分かりいただけたと思います。
職業リハビリテーションは、それまで就業の経験がなくても利用することが可能です。
そのため、障害や病気により退職し、再就職を目指す人以外に、初めての就職に自信を持つことが出来ない人でも利用することが可能です。
就職や再就職できるかどうかといったことや、就職した後に職場に定着することが出来るかどうかといった点について不安を持っている方は、この職業リハビリテーションのサービスを利用してみることをおすすめします。