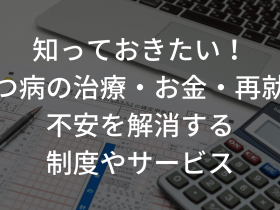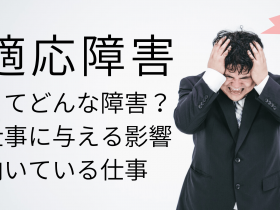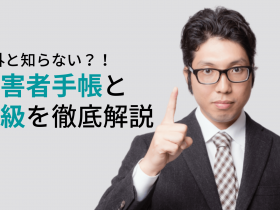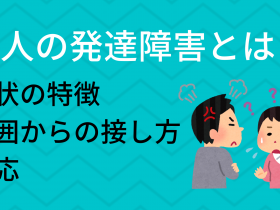朝起きられないのは甘えではない!関連する病気と対策について
更新日:2025年10月29日
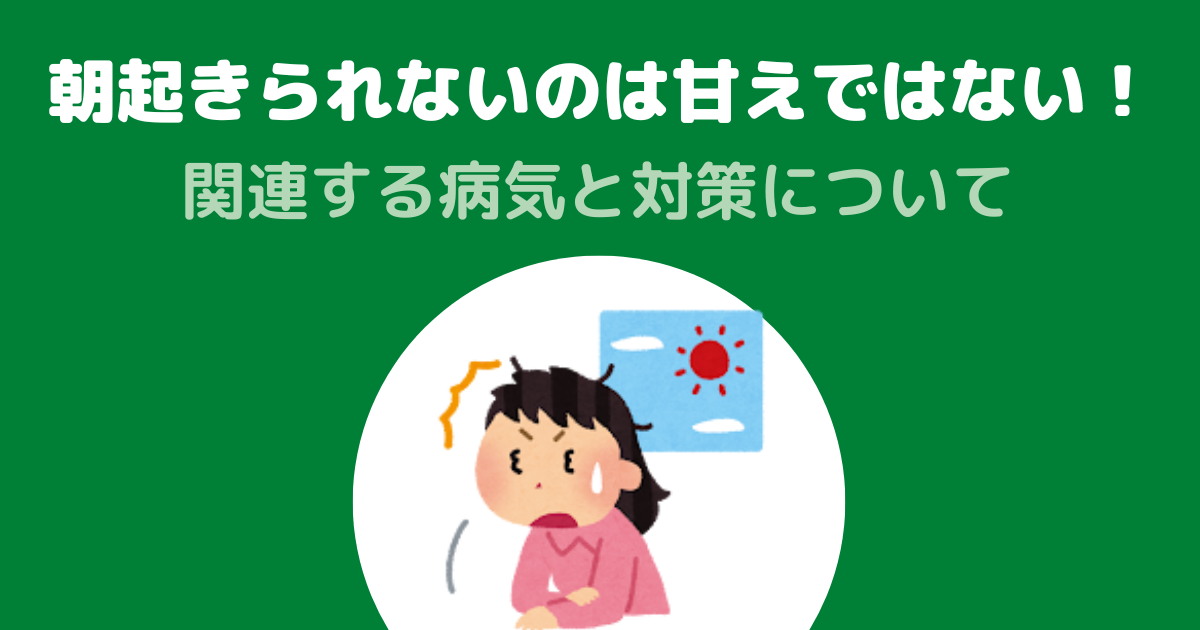
アラームを何度も鳴らしているのに、どうしても朝起きることができなくて、仕事や学校に遅刻してしまう。約束した時間に遅れてしまう。そんな経験はありませんか?大人になって朝起きられないと言うと、それは「甘え」だと非難されることがあります。しかし、根本的な原因がある可能性があります。本記事では、朝起きられないことの関連する病気や、朝起きられない時の対策法などについて解説します。
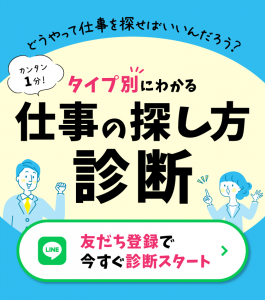
目次
朝起きられないのは甘えではない!その原因とは?
朝起きられないのは、「甘え」や「怠け」だけが理由でしょうか?大人が朝起きられない要因には、大きく分けて身体的原因、精神的・環境的な原因が考えられます。
身体的な原因
身体的な原因として、最も直接的なものが「睡眠不足」や「睡眠の質の低下」です。成人に必要な睡眠時間は、一般的に7〜8時間程度と言われています。しかし、現代社会ではさまざまな理由から、慢性的な睡眠不足に陥っている人が少なくありません。例え、布団に入って時間が長くても、眠りが浅かったり、夜中に何度も目覚めたりなど睡眠の質が低ければ、頭も身体も十分な休息ができません。
他にも、体内時計の乱れ、自律神経の乱れ、低血圧、睡眠時無呼吸症候群や適応障害などの病気が身体的な原因として考えられます。
精神的・環境的な原因
体だけでなく、心の状態や置かれている環境も、朝の目覚めや睡眠に大きな影響を与えます。特に、ストレスや生活習慣の乱れは、身体的な問題を引き起こす原因にもなります。
ストレスは自律神経のバランスを乱して、不眠や夜間覚醒、眠りの質の低下を招きます。十分な睡眠が取れないと、当然朝起きられなくなります。
現在の日本人は、「夜遅くまで起きている」「休日に大幅に寝だめする」など、生活習慣が乱れやすい環境にあります。特に、就寝時間と起床時間が日によって大きく変動する生活は、体内時計を混乱させて、睡眠と覚醒のリズムが不安定になり、朝起きるのが辛い状態を慢性化させます。
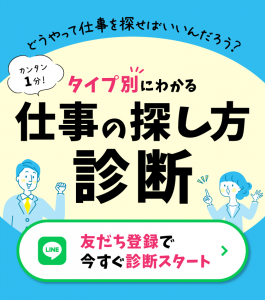
朝起きられないことに関連する病気
十分に睡眠時間を取っているのに朝起きられないのは、次のような病気が原因かもしれません。
睡眠時無呼吸症候群
「睡眠時無呼吸症候群」は、睡眠中に何度も呼吸が止まる病気です。具体的には、10秒以上呼吸が止まる状態を無呼吸といい、1時間に5回以上無呼吸の状態が発生する場合に「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。
睡眠時に何度も呼吸が止まると、睡眠の質が悪くなり、日中に異常な眠気を感じたり身体のだるさなどの症状を引き起こします。放置すると、血液中の酸素が欠乏することによって心臓や脳、血管に負担がかかって、脳卒中や狭心症、心筋梗塞などのリスクが高まります。
睡眠相後退症候群
「睡眠相後退症候群」は、一般的に望ましい時間に眠ったり起きたりすることが慢性的に困難な状態です。その結果、明け方に寝て昼過ぎに起きるなど、昼夜逆転のような生活になり、社会生活に大きな支障をきたします。
特に、若い方に多くみられ、夜なかなか寝付けないことで、学校や仕事に行くために朝に起きようとしても、まったく起きられない状態になります。また、無理に起きても眠気や頭痛、食欲不振などの症状を引き起こすことがあります。
適応障害
「適応障害」とは、環境の変化がストレスの原因となって、精神面や身体面の不調、行動面の異常が現れて、日常生活に支障が出ている状態です。「適応障害」になると、抑うつ気分や集中力の低下、無気力状態、情緒不安定、頭痛、吐き気、動悸、息切れなどさまざまな症状が現れます。
また「適応障害」には、不眠や睡眠過多など、睡眠障害の症状が現れるケースも多くあります。強いストレスが続くと、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたり、ぐっすり眠れなくなったりします。一方で、睡眠不足や疲労の蓄積、自律神経の乱れによって、過眠になってしまう人もいます。「適応障害」が悪化してうつ病になることもあるので、早めに医療機関を受診するのが重要です。
起立性調節障害
「起立性調節障害」は、自律神経の交感神経と副交感神経の働きのバランスが崩れることで、立ちくらみ、めまい、動悸、頭痛などさまざまな症状を引き起こしてしまう病気です。
人の身体は起き上がると重力によって血液が下半身に移動し、静脈で心臓に戻る血液の量が減って血圧が下がります。通常は、交感神経が作用して血管の抵抗を上げ血圧を維持します。しかし、自律神経の機能が低下すると血圧を維持できなくなり、その結果立ちくらみやめまいなどの不調が起きます。
起立性調節障害の原因と症状
この章では「起立性調節障害」の原因や症状について詳しく解説します。
起立性調節障害の原因
前章でも触れた通り「起立性調節障害」の主な原因は、自律神経の乱れです。交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、さまざまな症状が起こります。自律神経が乱れる原因としては、遺伝的な要素、思春期による体内のホルモンバランス、学校や友達、勉強などの精神的なストレスなどが挙げられます。
「起立性調節障害」は、思春期前後の子どもに多くみられる病気で、小学校高学年から増加し始め、中学生、高校生になるとおよそ10人に1人が起立性調節障害を抱えていると言われています。また、男子よりも女子の方が多い傾向があります。
起立性調節障害の症状
「起立性調節障害」の症状としては、以下のものが挙げられます。
・立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい
・立っていると気持ちが悪くなる。ひどくなると倒れる
・入浴時あるいは嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる
・少し動くと動悸あるいは息切れがする
・朝なかなか起きられず午前中調子が悪い
・顔色が青白い
・食欲不振
・臍疝痛(さいせんつう)へその周囲の痛みをときどき訴える
・倦怠あるいは疲れやすい
・頭痛
・乗り物に酔いやすい
症状には、「日内変動」があると言われており、午前中に強く午後になると徐々に軽減する傾向があります。また、夕方から就寝前はむしろ活動的になる場合もあります。また、「季節変動」もあるといわれており、季節の変わり目に悪化しやすく、雨や曇りなど気圧の低い日は、自律神経のバランスに影響を与える可能性があるといわれています。
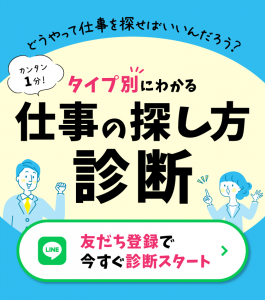
朝起きられないときの対策
朝起きられない時の対策法を原因別に紹介します。
睡眠時無呼吸症候群
「睡眠時無呼吸症候群」には、閉塞性と中枢性がありますがほとんどは閉塞性です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の主な原因は肥満です。肥満体型の人は、食事と運動を中心に体重を管理して標準体重を目指しましょう。
寝酒を控えることも大切です。アルコールには筋弛緩作用があるので、寝る前にお酒を飲むと、喉の周辺の筋肉が緩んで気道が狭くなり、呼吸が妨げられます。また、タバコも睡眠時の呼吸を妨げる可能性があります。タバコに含まれる化学物質は、気道の粘膜を刺激して炎症を引き起こします。喫煙者は非喫煙者と比べて、睡眠時無呼吸症候群になるリスクが高いので、禁煙をおすすめします。
睡眠相後退症候群
「睡眠相後退症候群」は、生活リズムが何かの原因で崩れた場合に発症します。次の点に注意しましょう。
● 寝る直前までのパソコンやスマートフォンの使用を避ける
寝る直前までパソコンやスマートフォンの画面を見ると、脳の覚醒状態が続いて寝付きにくくなります。
● 寝だめをしない、寝過ぎに注意する
休日だからといって昼過ぎまで寝ていることはありませんか?寝だめや寝すぎをすると、体内時計が乱れやすくなってしまいます。休日も規則正しい生活を心がけましょう。
● 目覚めたら日光を浴びる
「睡眠相後退症候群」では、ホルモンのリズムが乱れている可能性があります。朝起きて日光を浴びると、体内時計が整えられます。また、体内でメラトニンと呼ばれるホルモンの分泌がリセットされ、夜にメラトニンが分泌されやすくなり自然と眠りにつけるようになります。
適応障害
「適応障害」を予防するのに一番大切なことは、ストレスを溜め込みすぎないことです。日頃から、生活習慣を整えて、適度な運動やリラクゼーションを取り入れ、ストレスを発散する方法を身につけましょう。
現在の環境が、あまりにもストレスが大きいようであれば、ストレスが少ない環境に変える必要があります。
起立性調節障害
症状の重症度にもよりますが、軽症の場合には症状を悪化させないように、セルフケアを行ってみましょう。
・規則正しい生活を心がける
・血液量を増やすため、水分をしっかりとる
・毎日15分程度の散歩など、筋力低下を防ぐために運動をおこなう。
・頭を下げてゆっくり起立する。
・静止状態の起立保持は、1〜2分以上続けない。
・昼夜逆転を防ぐために、眠くなくても就床が遅くならないようにする。
朝起きるのが不安な方は、まずは生活のリズムを整える
「就労移行支援」は、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。障害や難病のある方が就職できるように、就労に向けたトレーニングや働くために必要な知識やスキルの習得、就職後の職場定着のサポートを行います。「就労移行支援」は通所型のサービスです。スケジュールに沿って継続的に事業所に通って、トレーニングや就職活動を行うことで生活のリズムを整えることができます。
「atGP(アットジーピー)ジョブトレ」は、障害者の転職サービス業界 No.1の「atGP」が運営する就労移行支援サービスです。うつ病・発達障害・統合失調症・聴覚障害・難病の5つのコース制なので、自分の障害と向き合いながら働き続けるスキルが身につきます。